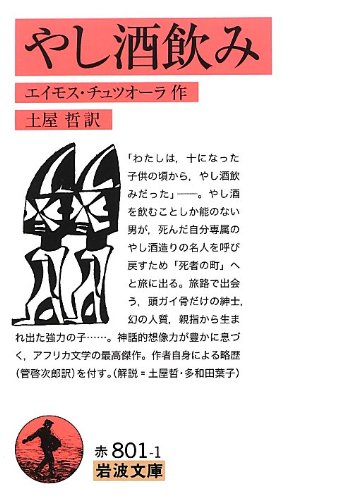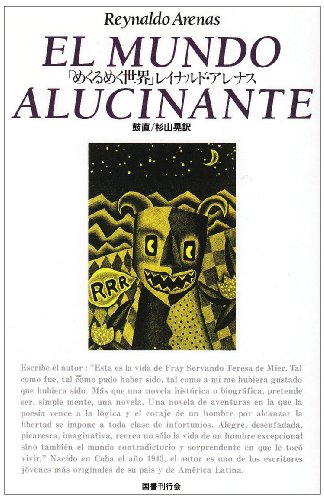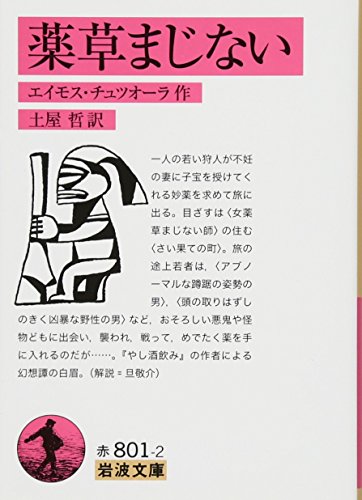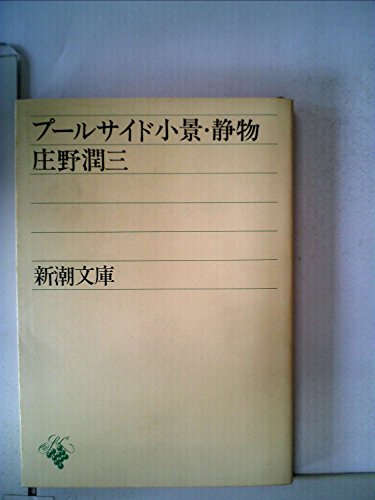Twitterで「生き方の問題」を激推ししている人を見かけて文芸誌で読んでから、私のなかで乗代雄介はそこそこ興味のある作家になり、芥川賞候補になった次作「最高の任務」も読んだ。
興味があると言っても、2作ともめちゃくちゃ好きなわけではなく、好きな点もあれば残念な点もある、やりたい方向性は分かるし良いと思うんだけど、読み終わると何だかスッキリしない気持ちになる……という立ち位置の作家。
で、2度目の芥川賞候補となった本作は発表当時から評判が良く、当然読まない選択肢は無かった。
168
中学入学を控えた亜美
小説家の語り手は妹と仲の良いお兄さんかと思ったら叔父かよ
ほのかに背徳の香り
「生き方の問題」ではモロにそうだったけど、乗代作品って正統的な行儀の良い純文学のわりに(だからこそ?)オタク臭さがあるんだよな。
自分がオタク的願望を勝手に読み込んでるだけ?
3
「でも大丈夫、今は机の引き出しにカギかけて隠してるから。おかーさんにもおとーさんにも言えないもんね」 p.6
「バレないもんね」を「言えないもんね」と発話する子供のリアリティ
ゴラッソ:ナイスゴールのスラング
4
静かなるドン:漫画
5
へー。そんな駅が実際にあるんだ。
もうわけわからん
6
臨時休校期間
うおお
商業の文学作品でコロナ禍ガッツリ出してきたの初めて見たかも。
いいねえ時代だねえ。テンション上がるわ〜
7
「旅の計画もパーだしさー」 p.8
逆にここはリアリティなくね?説明的すぎる
8
「家ではヨーロッパサッカーと、あとは夜におかーさんが帰ってきたら毎日『おジャ魔女どれみ』見るから一緒に見てる、今タダで見れるんだよ、おかーさんぼろぼろ泣くからおもしろいよ」 p.8
おかーさん泣くのかw 世代なんかな
8
もちろん、相手が本当に強い時はほとんど何もできずにつぶされる。そのふてくされ寸前の顔を見るのもまた楽しみだった。 p.9
性格悪いというかこわい
9
算数じゃなくて数学だ。 p.9
これ発話じゃなくて地の文なのか。
その時に口に出して訂正せず内心でツッコんだだけなのか、口に出してるけど
カギカッコつけずにいるのか、それともその時はまったくツッコみもせず、当時を思い返してこの本文を書いている〈今〉初めて気付いてツッコんだのか……
118
こんな状況では、「卒業の姪と来てゐる堤かな」という気分でもなかった。 p.9
「卒業の兄と来てゐる堤かな」・・・芝不器男という明治大正の
俳人の俳句らしい
9
合宿で本盗んできたから返しにいくとか、状況・物語の大枠設定が意図的なほどに無骨というか、突貫工事感がすごい。
あえてやってるのかと勘ぐっちゃう
自分に懐いている小学生姪と2人旅っていかにもエロゲやん
11
舞台がまさに自分がいま乗ってる
常磐線で運命を感じた。
「そろそろ
我孫子だ」のタイミングが作中と現実で完璧に一致していた!
14
読みながら作中の舞台を歩きたいな〜〜〜
14
小説中の2人が訪れたところへ私も訪れ、小説を読み進めながら2人と同じ道を一緒に歩く。
118
そういや「最高の任務」も家族で電車で旅する話だったな。
「生き方の問題」は毎夏の帰省の話だったような気がするし。
乗代さんは旅が好きなんだな。
14
人気のない風景を描写するの、めっちゃ良いな〜〜〜15
この人のように文章で情景描写はしないけど、離島やド田舎に一人旅して田園風景や何気ない交差点とかを写真に撮ったりその場で眺めてエモさを楽しんだりはする。118

『旅する練習』には特に関係のないT字路。カーブミラー大好き
118
志賀直哉の邸宅跡は台地の上ではなくその裾あたり、沼辺からものの数分のところ、
我孫子駅から
手賀沼に出る手前で曲がった崖下の道にある。今はその跡地として、裏手の崖地の木々も含めて整備され、何度か移築されたという凝った書斎だけはその姿を保存されている。母屋はもうないが、その実寸の間取りがコン
クリートで示されていた。 p.15

亜美は最初は土の上で、それから間取り図の土間の辺り、日当たりのいいところに場所を移してリフティングをしていた。別に
志賀直哉も、自分が生活していた百年後に小学生がボールを蹴ったからって怒りはしないだろう。 p.16
しかし、そう言っておいてすぐに
手賀沼に出ることはなく、「
瀧井孝作仮寓跡」の案内を見つけ、また崖の方へ上っていくことになった。 p.17
志賀直哉邸跡から少し東、子の神古墳群の円墳の二つがはっきり残っているところに、
瀧井孝作の仮住まいがあったという。今、一帯は公園を兼ね、民家はあるが、生け垣と様々な木が立ち並んで落ち着く雰囲気だ。そこに一台だけ置かれたベンチに座って書いている。 p.18

そのベンチ。季節が微妙にずれていて、
サザンカや
トウネズミモチは見つけられなかった(私が植物に疎いだけかもしれないが)。118

『旅する練習』には特に関係のないエモい下り階段。118
「せめて回数だけでもそっちに控えといてよ」
「なるほど」私は感心しながら記述の最後にその数字を書き加えた。 p.19
ああ、風景描写の最後の数字は亜美のリフティングの記録だったのか。
19
我々は再び崖を下り、住宅街を歩いて手賀沼に突き当たった。とはいえフェンス越しの堤が高く、水は見えない。散歩のための細道に、低い生け垣だけをはさんで家々の庭が面している。 p.20

その突き当たり(堤の奥が
手賀沼)。ここで作中の2人は左へ歩いていくが、時間の関係上、私は右の道から
我孫子駅に戻った。いつか時間があるときに再チャレンジしたい。
ここからは、再び本のなかで2人の旅路を追いかける。
118
寝る前に、亜美は日記を書いた。読ませようとはしなかったから、ここには載せないつもりだ。ただし、亜美の方から読ませてやろうと見せてくれた日記についてはその限りではない。これから書いていく先にそれが一つでも待っているということだ、私を大いに励ましてくれる。 p.33
最後の1文が気になる。つまり、これから先に亜美の日記があることは確定しているということか。それは、この練習の旅をしている〈今〉に対して、この本文(『旅する練習』)を書いている〈今〉は未来に位置しており、旅がすでに終わって、どのようになったのか全てを知っている状態で、基本的にはあたかもこの先を知らない体で旅程を記していることを意味する。
乗代は<書くこと>に極めて自覚的・批評的な眼差しを向ける作家だ。
『生き方の問題』は、
書簡体小説として<書かれている今>と<書いている今>、そして<読んでいる今>がテクストから三位一体となって湧き上がる小説だった。
本作ではそれがさらに重層化し、回想の回想の回想の回想……といったややこしい
入れ子構造になっている。
と書いたけど、本作でもこうした作風が端々から滲み出ている。
「旅の全貌をすでに知っているけど、知らない体で旅路を記す」というのは、今まさに私がこうして感想記事を書いている行為と非常に似ていると感じる。
「小説の全貌をすでに知っているけど、先の展開を知らない体で感想を書く」こと。
これは私のポリシーでもある。
普通の書評ブログ、普通の読書感想文というのは、その本を最後まで読んでから、自分なりに展開やテーマなどを咀嚼して、文章にまとめる形式がほとんどだと思う。
しかし、この記事や他の記事を見ればわかるように、私はこのブログで、そうした普通の体裁をとっていない。読書中に気になった文に付箋を貼っておき、その部分を引用し、そこを読んだときに感じたことを、どんな些細なことでもそのまま書く。
そもそも小説のあらすじを私は説明しない。
その本を読んだことのない人からすれば、当然、私の記事は読みにくい。どういう流れでその文があるのか分からないからだ。(読んだことのある人でも読みにくいだろう)
私がこうした「実況」の体裁で感想記事を書くのは、なにも読者へ嫌がらせをしたいわけではない。
私は読書を「私とその本との間で起こった出来事」だと捉えている。
そして、私がブログに感想を書くのは「私とその本との間で起こった出来事」を鮮明に記録するためだ。読者に本を紹介することが目的ではない。
だから、もっとも重要なのは「その本を読んでいる最中に感じたこと」である。「その本を読み終わって感じたこと」ではない。それは二の次、三の次だ。
小説の序盤の記述に引っかかって、その疑問を書き留めたとする。最後まで読めば、その疑問はまったくの勘違いだった、ということはありふれている。では、序盤で浮かんだ疑問は無駄なものだったのか?書き留める必要はなかったのか?
私はそうは思わない。たとえそれが勘違いだったとしても、後に自己解決するとしても、「そのとき」その疑問が浮かんだことは事実であり、読み終えたら忘れ去られてしまう、その寄る辺ない"事実"こそ、もっとも優先的に保護すべきだと私は思う。
21世紀に生きるわれわれの価値観(ex.地動説)で、昔の人々の価値観(ex.天動説)を「そんな明らかに間違ってること信じてるなんてバッカじゃねーのwww」と断罪することは極めて愚かな行為だ。
それとまったく同様に、ある本を読み終わっての感想をもって、その本を読んでいる途中の感想を否定したり無化したりすることは、私はなるべく避けたいと思っている。
さらに言えば、「その本を読み始めてすらいないときにその本に抱いていたイメージ」だって非常に重要だと思っている。だから、私はなるべく「どういう経緯でその本を知り、その本に出会い、手に入れ、興味をもち、読む始めるに至ったのか」や「読む前にその本・作家にはどのようなイメージを持っていたのか。どんな情報をネットや知人経由で知っていたのか」を書き留めようと思っている。全ての記事で出来ているわけではないが……
「読む前の感想」「読んでいる最中の感想」「読み終わっての感想」
私はこれら3つとも尊重したいと常々思っている。
また、こうした思想は「本は再読してこそ価値がある」とか「1冊の本を真の意味で"読み終える"ことは絶対にできない」などといった、
ボルヘス辺りが言ってそうな思想とも相性がいい。再読を前提にすれば、「1回読み終わっての感想」は「2回読む前の感想」と同義になるからだ。読む前と読んだ後がイコールで結ばれて、無限の再読サイクルによって両者の差異が無化されていけば、〈私〉とその〈本〉のあいだの結びつきは開かれており終わることがない(し、始まりすらもない。1ページ目をめくる前から「読書」は始まっているのだから)ことは自明になるだろう。
(※しかし私は現状、ほとんど再読はしていない。他に読みたい本がたくさんあるから…)
いま、『旅する練習』の感想を離れてこうして長々と自分の読書観・ブログ観を語っているのも、全ては『旅する練習』を読んでいる最中に考えたことだからである。
私は自分語りが好きだ。ブログなんてそもそも自分語りのための場だろうに「ブログで隙あらば自分語りするのは恥ずかしい」などという風潮があるのは到底理解できない。(そんなに自意識の開陳が嫌ならそもそもブログをやるな。インターネットをやるな)
本作『旅する練習』の語り手たる「私」も、よく自分語りをする。自分語りというか、旅の最中に風景などから自由に連想したことを書き留める。
瀧井孝作の名を見て
講談社文芸文庫の解説の
古井由吉を思い出したりとか、有名な木を見て
柳田國男の学説を引用したりとか、正直言って「知識自慢か?」と鬱陶しくも思う。
しかし、それこそが必要なのだ。それが旅をする理由であり、価値なのだ。
客観的な土地や場所から、自分で自由に想像をふくらませ、有る事無い事に思いを馳せること。他の誰でもないこの私が、その場所に行って自分の足で歩いたことを保証するのは、そういった「自分語り」ではないのか。
だから私は、あらすじを説明して、読んだ後の感想や考察を、読んでいない人にも分かるように整理してまとめるやり方はなるべくしたくない。(するときもあるし、他人がそれをすることを貶すつもりはない。私の愛読している多くの読書ブログはその王道の形式である)
私は、本文とは関係のない自分語りができればできるほど、良い本だと思う。
その土地自体とは関係のない自分語りができればできるほど、良い旅であるのと同様に。
以上のことは、120ページ辺りまで読んだ段階で、考えて書いた。
本作がどう着地するのか、私はまだ知らない。
この「実況」としてはまだp.33までしか進んでいないので、今これを書いている私は、約90ページ分を「読んでいない体」で実況をしている、ということだ。
もちろん、理想的には、読んで感じたことを、感じた瞬間に書き付けることができれば最高だ。1文ごとに、1文字ごとに感じたことを文字に起こすことが。
しかし、それは現実的ではない。
だから、その場で感想を書き起こせないときは、とりあえず付箋を貼り、読み進め、あとでこうして「先を読んでいない体で」その瞬間の感想を書き付ける。
で、私が今やっていることと、『旅する練習』の語り手たる「私」が本書でやっていることはほとんど同じことだと思ったのだ。(やっと戻ってきた)
「これから書いていく先にそれが一つでも待っているということだ、私を大いに励ましてくれる。」という未来からの1文は、そうした「先を知らない体」がにわかにほころんで、「すでに旅の全容を知っている私」が一瞬顔を覗かせた描写であると思う。
こうした「未来からの言及」は、地動説と天動説の例の通り、あまりよろしくはない。そうした行為は暴力的であるとすら言っていい。
しかし、そもそも「書くこと」には原理的にこうした暴力性が伴っている。
「私は〜〜した。亜美は〜〜した」という過去形での描写はそれ自体が〈今〉から過去を振り返って(=見下して)断定するきわめて暴力的な行為である。
私は、本作の端々に、こうした「書くこと」で原理的に立ち上がってきてしまう複数の〈私〉=時制のズレ=暴力性と、それを隠蔽しようとする態度への葛藤を強く感じる。(それは、私がいつも読書の感想を書くときに強く感じていることだ)
現在形で「私は〜〜する」などと書くのは、前述の「読んで感じたことを、感じた瞬間に書き付ける」ことの非現実性と同様の理由で棄却される。どんなに「その瞬間」の現在時制を徹底しようとしても、語り手が認識したあとに描写しているのだから、それは「過去」のことである。本当は過去形であるのを現在形で取り繕うくらいなら、はじめから過去形で描写したほうがよほど素直だ。
※
ヌーヴォー・ロマンなど、現在時制に取り組んだ小説は数多くあるだろう。例えばモニック・ウィティッグ『
子供の領分』は全編が子供による現在時制一人称の語りだ。しかし私はこうした小説に詳しくないので、ここで何か評価を下すことはできない。
※過去形でも現在形でもない、未来形の語りも多くの実例があるだろう。私がいま思いつくだけでも、リャマ
サーレス『黄色い雨』やカルロス・
フエンテス『アルテミオ・クルスの死』は部分的に未来形の語りを採用している。ただ、「〜〜するだろう」という未来形の語りは、人物の将来の行動を予言できるほどの超越性・特権性をどうしても帯びてしまう気がする。そして、ここでの超越性・特権性とは上で言う暴力性のことだ。
そういえば今思ったんだけど、「旅をすでに終えた私」が「旅の最中の私」を描写する構図のアナロ
ジーとして、旅の最中に「成人男性たる私」が「未成年女子である亜美」の保護者として付き添う構図を理解できないか?
〈書く〉という行為においては「現在」が「過去」に対して特権性を持っているように、現実では「年長者」が「年少者」に対して特権性を持っている。保護する/される という構図はその特権性・権力勾配の言い換えに他ならない。
また、年齢だけでなく、「男性」が「女性」に対して持っている特権性……みたいな
フェミニズム的な構図も見出だせる。
それから、亜美は運動(サッカー)が大好きで読書や日記などは苦手なのに対して、「私」は小説家であり様々な教養を持っている。つまり、(適切な言葉選びではないが)「文化系の人間」が「体育会系の人間」に対して持っている特権性・優越性みたいな構図も見出だせるのかな。
学生生活とかでは逆にイケイケの体育会系(
陽キャ)が文化系(
陰キャ)を抑圧しがちであるという
ステレオタイプがあるように思うが、ここでのポイントはやはり「書く」というフィールドの話だ。文字として残る言論空間においては当然ながら圧倒的に文化系が有利で、体育会系を好きなようにこき下ろすことが出来る。
……いやまぁ作中で「私」はそこまで亜美の学のなさを馬鹿にしてもいないと思うけど。字が汚いとか、
真言を忘れるとか、日記をサボるのに対して少し
咎めてたりはする。
まぁあまり良いア
イデアじゃなかったけど、「小説では本好きが肯定されがちだけど、それって自分のフィールドで特権性を誇っている浅ましい行為でもあるよね」という自戒としては少し価値があるかもしれない。
118
「今の、ぜったい日記に書くからね」
実際、この話は日記に書かれた。むしろ、亜美の日記によってこの会話を思い出したから私はこうして書いていると言った方がいいかも知れない。 p.44
ここも露骨に、書かれている今と書いている今の時間的なズレを主張している。しかも、本書に出てくる「書きもの」は、
①「私」の日記(=『旅する練習』)
② 亜美の日記(中学の課題)
③「私」の風景描写練習
と、少なくとも3つある。これらが相互に影響しあって重層的にテクストを形成している。「私」だけでなく亜美という別人も書く主体になっており、筆者間の権力関係をも扱っている点で、前作『最高の任務』から更に問題意識が進んでいると言えるかもしれない(前作をあんまり覚えてないけど)
(亜美が忘れないよう手に書いた真言や、みどりさんが残したメモ書きなども、ミニマムな「書きもの」として追加できるかも)
118
それは珍しい光景かも知れないが、思い浮かべた以上、あんまり出くわしたいものではない。起こってもいないことを考えて、その通りだとか違っていたとか、そういう気分から離れたくて歩いているのに。 p.45
わかるようなわからないような。「答え合わせ」の煩わしさ、やるせなさからの逃避としての旅=読書
118
途切れた文を目にするたびに亜美の「あ」という声が聞こえる気がする。 p.51
露骨過ぎて笑っちゃうNo.3
118
みどりさん
女子小学生だけでなく女子大生まで出てきた。オタクの妄想か?(元気な亜美とは対照的な人見知りキャラってのもいかにも〜〜〜)
118
「アビ?」とその人は興味深そうに言った。「どうやって書くの?」 p.55
うわ〜〜〜〜ってなった。露骨とかそういう次元ではない。狙いすぎであることを隠そうともしないという狙いすぎ感
要するに「書かれている今」と「書いている今」だけでなく、この文章を「読んでいる今」すなわちわれわれ読者とのズレを意識させようという魂胆よな。最初に説明するほうが自然なのに敢えてそうはしなかったということだから。
118
p.83
亜美ちゃんとみどりさんのやり取り、いいな〜〜〜。「私」いらなくね?(百合の間に挟まる男は許せない並感)
118
我々はとりあえず、ガードレールの外側の土手下から橋のぎりぎり、等間隔に三本立っている堰柱の陰までやってきた。 p.84
この橋はたしかに歩道がなく、渡るのは大変そうだった。
3人が車の往来を見ながら立ってたガードレールの端っこってここか〜〜〜などとテンションが上がった。
118
その謎はともかくとして、書き残されない常人の感覚というものは、私の興味を大いにかき立てるものだ。 p.92
「書くこと」に焦点が当たるとき、それは同時に「書かれなかったこと」が視界から外れていることを意味する。そうした〈今、ここ〉の外部へのまなざし、目配せ。相変わらず露骨だけど。テーマ性はすごく好きなんだけど、もうちょっとさり気なく書けないかなぁと乗代作品を読んでいるといっつも思う。
あと、「書くこと」によってその土地に当時住んでいた人々の記憶を記録に残す切実さ、みたいなテーマは『
君の名は。』じゃん!と思いながら読んでる。
キャラだけでいったら実質『
よつばと!』なんだけど。
118
私しか見なかったことを先々へ残すことに、私は──少しあせっているかも知れないが──本気である。そのために一人で口を噤みながら練習足らずの言葉をあれこれ尽くしているというのに、そのために本当に必要とするのはあらゆる意味で無垢で迷信深いお喋りな人間たちだという事実が、また私をあせらせる。 p.97
ん〜〜〜??? 意味深〜〜〜〜〜〜〜〜
実は、本書を読み始めの頃に母親に薦めて、私より先に読み終えたんだけど、「最後がどんでん返しで〜〜…改めて最初から読み直したら確かにところどころで〜〜…」というメタバレ(「この作品はネタバレ厳禁です!」というメタ情報によるネタバレ)を食らっている。
いまこの文章を書いている時点では、わたしは118ページまでしか読んでおらず、「どんでん返し」に到達していないが、メタバレされているので、オチの予想は嫌でもしてしまう。
「そのために本当に必要とするのはあらゆる意味で無垢で迷信深いお喋りな人間たちだ」という部分は、やっぱりそういうことなんかな……
118
水郷の町 佐原を舞台にした
小島信夫の短編『鬼』読んでみたい。
いま
Kindleで探したら『馬』読書会のために『
アメリカン・スクール』を購入していたのでいつでも読めるじゃん
118
そして、本当に永らく自分を救い続けるのは、このような、迂闊な感動を内から律するような忍耐だと私は知りつつある。この忍耐は何だろう。その不思議を私はもっと思い知りたいし、その果てに心のふるえない人間が待望されているとしても、そうなることを今は望む。この旅の記憶に浮ついて手を止めようとする心の震えを沈め、忍耐し、書かなければならない。後には文字が成果ではなく、灰のように残るだろう。 p.104
「本作の核心」っぽいの来たな……
118
馬頭観音から口数も減ってかなり速いペースで歩く亜美の背中を思い浮かべ、「運命を承認するかのごとく」と引きながら、私は少し複雑な気分だ。本当は運命なんて考えることなく見たものを書き留めたいのに、私の怠惰がそれを許さない。心が動かなければ書き始めることはできない。そのくせ、感動を忍耐しなければ書くことはままならない。 p.118
でも分かる気がする。
読書中に感動した一節には付箋を貼って、その感動を後々に残るようにしたいのに、「付箋を貼る」とか「後々に残そう」と思うその行為じたいが、感動を一歩引いた目線で客観視する作用があり、その瞬間に最初の感動は薄れて、決定的に損なわれてしまう。書くという行為は、常にこうした「熱さ」と「冷たさ」の対流によって駆動していて、それをここでは「感動」と「忍耐」で言い換えている。・・・と、私は読んだ。
118
ちょうど鎮守の森を一つ回り込み南進する道に入ったところで、小高い林が囲む広い田園の視界が右から左へと開けていく。 p.119
三叉の道で
田圃に背を向け、小山に通された道を上っていく手前に観音寺はあった。 p.119
の三叉路。左が来た道。後ろが「小山に通された道」。右が観音寺訪問後に進む道。168
もう反対側の木立の前の民家まで来ていたが、振り返って春に備える田の先へ目を向けている。見れば、ちょうど田園に視界の開けた辺り、我々も通ったその一本道を人が一人歩いていた。夏だったら青い稲に隠されてきっと見えないほど、小さい赤い点になって。 p.122

「反対側の木立の前の民家」。亜美が振り返ったところ。

亜美が振り返った視界はおそらくこんな感じ。画面の真ん中らへんにみどりさんが歩いていると思われる。どんだけ視力いいんだよ……
168

上の3箇所(と観音寺)の位置関係はこんなかんじ。
亜美は走り出した。(中略)角を曲がって、こちらに少し膨らんだ林の前を書けていく亜美には、顔を上げる素振りもなく歩いているみどりさんの姿は見えなくなったろう。林を回って、今度は私から亜美の姿が消える。やがて、抜けるような青空に、みどりさんを呼ぶ声が遠く高く響いた。 p.122
という描写を完全に理解した。
168
もちろん、そこに座り込んで書くことなんて思いもよらない。しかし、状況というものは刻一刻と変わるものだ。
川の流れのように季節は巡り、今いる者はもういない。私は二ヶ月以上経った後でまたこの場所を訪れ、あの時三人で立っていた場所に今度は一人で座り、忘れ難いその時のことを必死に思い出しながら書いた。 p.128
え、二ヶ月後にもう一度「私」は旅をしてるって既出情報だっけ。
「書いている今」の時制がさらに錯綜する〜〜〜
168
「願ったんなら叶えてしまえや」by Orangestar
我々の発願は、それをもたらしたものは、そこから続く日々の行いとは何か。…発願なしには信心も練習も開発も始まらないが、度重なる行いの中に願いは少しずつ溶けていく。…しかし、こうした透明な成就が、そんなことを知る由もない人々の営みが、不思議と当人たちを慰めてくれることもある。 pp.147-148
…は中略部。「透明な成就」はなかなか興味深い言葉だ。
168
p.168
読み終えた。
いや〜〜そう来るか〜〜〜
外れた方のオチ予想を書いておくと、亜美ちゃんもみどりさんも実は存在せず、「私」が一人で歩いているのみ…という2人は空想の産物エンドを覚悟していたけど、もっとありきたり……というか、ストレートなやつだった。はいはい、そっちね。
『最高の任務』の感想では「本作は軽いミステリ・謎解き要素と、叔母や家族との絆といった感動的要素が盛り込まれて、比較的キレイにまとまっているが、それが逆に作品をこじんまりとさせている」 と書いたが、本作もわりと安直な感動要素(?)で最後に総括した感じ。
ん〜〜〜駄目とは言わないけど、なんだかなぁ。
もちろんそれが、長々と上で書いた、書くことによって記憶に残す切実さ、みたいなものに繋がるとか、そういうロジックは分かるんだけど(だって作中でめちゃくちゃ説明してるし)……
あの最後が無くとも、本作でやりたいテーマ性は十分に表現できていたと思う。逆に、ああした終わり方でなければ読者に本作の核心が伝わらないとか、不十分であると思っているのなら、もう少し小説を、読者を、自分を信じてもいいのでは?と不相応にも思う。
こういう風じゃない乗代作品も読んでみたいと強く思う。テーマ性にはすごく共感できる分、乗代さんにはもっと先へと行ってほしい。偉そうだけど、率直な感想として。
にしても、旅をしながら書いていく紀行文の形式はすごくいいな。じぶんも「旅する練習」をやってみたい。
乗代さんで読んでないのは『十七八より』『本物の読書家』『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』。
なかなか良いと噂のデビュー作『十七八より』はKindkeで積んでいる。