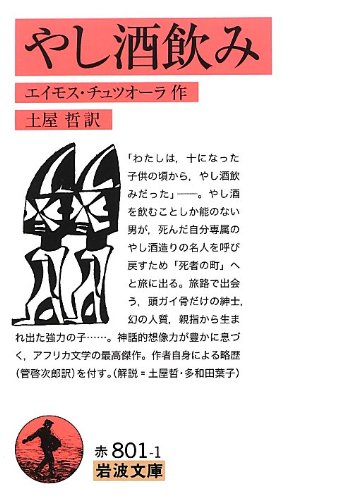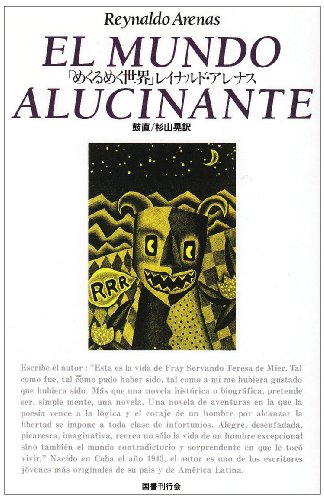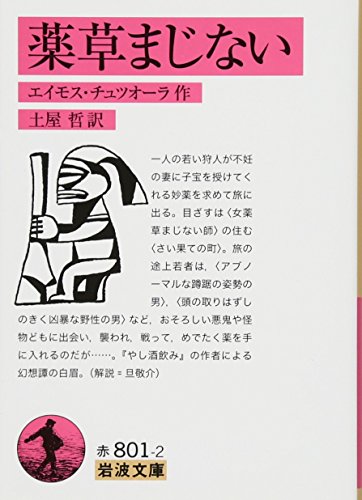尊敬する読書家の知り合いが「やっぱり『やし酒飲み』みたいな小説の語りが最強だよ」的なことを言っているのを聞き、翌日図書館で単行本版を手に取り、すぐにこれはとんでもない作品だと確信したため生協で岩波文庫版を買った。
わたしは、十になった子供の頃から、やし酒飲みだった。わたしの生活は、やし酒を飲むこと以外には何もすることのない毎日でした。 p.7
常体と敬体が混ざっていて不思議な語り。これ原文の英語どうなってるんだ?
父は、わたしにやし酒を飲むことだけしか能のないのに気がついて、わたしのため専属のやし酒造りの名人を雇ってくれた。彼の仕事は、わたしのため毎日やし酒を造ってくれることであった。 p.7
最高じゃん。酒好きだったらもっと楽しいのかな。
父が死んで六ヶ月経ったある日曜の夕方、やし酒造りは、やし酒を造りにやし園へ行った。やし園に着くと、彼は一番高いやしの木に登り、やし酒を採集していたが、その時ふとしたはずみに木から落ち、その怪我がもとでやしの木の根っこで死んでしまった。 p.8
「やし」がゲシュタルト崩壊するこの冗長性すごいな。「わたし」が実際に見ていないであろうことを何で語れるのだろうと思うけど、まぁここは木の根元で死んでた状況から推測したとしても不自然じゃないか。
死んだやし酒造りが住む町を目指して旅に出る。なんだ、酒飲んでるだけのニートかと思ったら意外とバイタリティあるやん
神である彼の家に、人間が、わたしのように気軽に、入ってはならないのだが、わたし自身も神でありジュジュマン juju-man だったので、この点は問題がなかった。 p.11
クソワロタ。おまえ神だったんか。先言えよ〜〜(ジュジュマンてなに?)
実は神で、次から次へと吹っかけられる難題を割とサクサクこなしていく様はなろう小説っぽくもある。
わたしがベルを持って帰ってきたのを見て、老人と妻はびっくり仰天し、同時に、また強いショックを受けた。 p.12
こっちがびっくり仰天だよ。「びっくり仰天し、同時に、また強いショックを受けた」って何だよ。「彼は頭痛に悩み、またそれだけではなく、頭がひどく痛むことに苦しんだ」みたいな重言表現。驚き具体を強調するための修辞だろうけど、こんな風に平然と繰り出されるから驚く。言葉とは、世界の感じ方、世界の語り方そのものだという事実を思い知らされる。この小説の語りにおいては我々の常識を捨てなければいけない。
さて、どの道が「死神」の道なのか、皆目見当がつかず、途方にくれていたのだが、たまたまその日は、市の立つ日だし、市場へ行った連中がそろそろ帰ってくる頃だということを思い出し、わたしは道路の合流点のど真ん中で、頭、左手、右手、両足をそれぞれ五つの道路の方向に向けて大の字になって、ねたふりをしていた。 p.13
ここ、『重力の虹』で発散手前のスロースロップが十字路の中心でねそべってロケットの落下を待つ印象的なシーンを思い出した。(なんかそんな感じのくだりあったよね?)
「死神」の道がどれか調べる方法としても面白い。
「死神」の家から「死神」を連れ出したその日から、「死神」には永住の場所がなくなりました。わたしたちがこの世で「死神」の名をよく耳にするようになったのは、そのためなのです。 p.18
クソワロタ。お前のせいじゃねぇか。こういうことをいけしゃあしゃあと語られるのほんと笑う。
完全な紳士に変装した「頭ガイ骨」の跡を追って家までついて行ったからといって、この娘をとがめることは、到底わたしにはできないことだった。もしわたしが女だったら、わたしだって彼の跡をつけて、彼の行く所まで行っただろうし、その美しさ故に、この紳士が戦場へ行けば、敵だって、彼を殺したり捕えるようなことはしないし、爆弾を落とそうとしていた男も、彼が町にいるのを見れば、彼のいる所には爆弾を落とさないだろうし、もし仮に落としたとしても、爆弾の方で、この紳士が町を去るまでは炸裂しないだろうから。 p.28-29
しびれる〜。「もしわたしが〇〇だったら〜〜」で軽い同情や感情移入から始まり、徐々にドライブしていって爆弾まで行き着く。荒唐無稽さをシームレスな語りで緩和している。(し、何より好きなのは、おそらく「狙ってやっていない」だろうこと。実際どこまで推敲していたかは知らんが、私にそう思わせてくれた時点で勝ち)
「頭ガイ骨」どもは、奇声を発し、大きな石のように地面をころがりながら、森の中を迫ってきて、すんでのところでわたしを捕えそうになり、また仮に、そのように逃げまわってみても、所詮やがては捕まってしまうことが明らかになった時、わたしは、娘を子ネコに変えて、わたしのポケットの中に入れ、わたし自身は、英語でいえばさしずめ「スズメ」にあたる、とても小さな小鳥に姿を変えることにした。 p.33
英語でいえば、か。語り手は英語ができるのか?元はどの言語で語っている設定なんだ。これだけ言語の異質性を全面に押し出した作品だけに、こういう些細な点はめちゃくちゃ気になる。
ある日、やし酒を採集していた農園までわたしについてきた妻のふくれ上った親指に、やしの木のトゲがささった時、驚いたことに、突然親指が破裂して、そこから男の子が生れてきて、まるで十歳の子供のように、わたしたちに話しかけはじめるのだった。
親指から地上に降り立つ間に、その子供は、三フィートとちょっとの大きさになり、声は、まるで誰かが鋼鉄のハンマーで、カナトコを叩いているような、よくききとれる声になっていた。 p.37-38
とつぜん指が「浮袋のように」ふくれ上るのは目取真俊「水滴」を思い出す。
指が破裂して子供が出てきたこと自体より、地上に降り立つ間にみるみる成長するスピード感にやられた。しかも「成長」をあらわすために「三フィート」という視覚情報だけでなく、「まるで誰かが鋼鉄のハンマーで、カナトコを叩いているような」声という聴覚情報を2番目に付け足すのが見事。
この子供ほんとすげー不気味かつ恐ろしかった。本作に登場するキャラでいちばん怖いかもしれない。
赤ん坊をつれていった所に、人間になぞらえていえば、「ドラム・ソング・ダンス」という名の、三人の、わたしたちと同じ種類の生きた生物がいた。 p.46
ダンス!!!いいねぇ。そうか、こういう原始的な三要素挙げるとしたらその3つになるんだ。ヒップホップの四大要素的な。
わたしたちは火に変わったのだから、空腹などは感じないだろうなどとお考えにならないで頂きたい。わたしたちが火であることは、まぎれもない事実ではあったが、ひもじさは人一倍感じていたのだった。だからといって今すぐに、人間の姿に戻ったならば、即座に白い生物たちに、殺されるか危害を加えられることは、火をみるより明らかだった。 p.53
やかましいわ!!!・・・とツッコんでふと、いや待て原文はどうなってるんだ?と思い至る。
その男は、王様に命じられた通りに、情容赦なくわたしたちを突き刺したので、わたしたちは苦痛を感じ、思わず口を利いた。ところが、わたしたちの声を聞いたとたんに彼らは、まるで爆弾が破裂したように、ドッと笑い出した。そしてその夜わたしたちは、人間にみたてて言えば、その「笑の神」と、熟知の仲になったのだった。わたしたちを笑うのを彼らは、止めてしまったのに、「笑の神」は、二時間も、笑いをやめなかったからです。 p.56
さいしょ「彼ら」が「笑の神」なのかと思ったけどどうやら1人っぽい。文の連なりで巧妙にずらしてきてる……というよりも、やっぱり自分が文章に求める整合性がここでは通用しないと考えたほうがいいだろうな。
それに衣裳をまとった時の「島」の生物たちのあでやかな姿は、まるで人間そっくりで、彼らの子供たちの晴れ姿を見ているうちに、あなた方はきっと、子供たちがいつも、舞台劇を上演しているのだという錯覚に、捕えられることでしょう。 p.59
いきなりこっちに話しかけられるとビビる。それに「島」の謎の生物たちの「子供たち」が舞台劇を上演している錯覚って描写もなかなか怪奇幻想めいててすごいな。
──ところが、途中で、膝に目がくっつき、モモから腕が生え、おまけにその腕が足より長くてどんな木のテッペンにでも届くという、後ろ向きに歩く男に出くわして、またまた度ぎもを抜かれたのだった。 p.69
いやいや情報量がすごい……!降参降参
そこでもう少しその道を歩き続け、今までのように森林の旅をつづけるためには、そろそろ左へ折れ曲がらなくてはならなくなった時、どうしたことか、わたしたちは曲がることもできず、さりとて停止することもならず、また後ろへ戻ることもできなくなってしまい、道はただ一つ町に向って前進あるのみということになってしまい、とまろうと全力をつくしたが、駄目だった。 p.73「不帰の天の町」への旅
この未知の生物たちは、何かにつけて、人間の逆張りを行くのだった。たとえば、木に登る時には、まずハシゴに登っておいて、そのあとから、ハシゴを木にもたせかけたし、また、町の近くに平坦地があるのに、家はすべて、傾斜の急な丘陵の中腹に建てたし、そのために居住者も落っこちそうなぐらいに、家は傾斜し、事実、子供たちは、家からいつもころがり落ちていたが、親たちは一向におかまいなしといった調子だった。 p.74
おもろい。「事実、子供たちは、家からいつもころがり落ちていた」じゃねぇよ・・・こういう真顔ユーモアすき
妻の存在感の無さ。それでいて、夫にひたすら従順に影のように付き従っているから存在感がないというわけでもなく、お互いに自分第一で精神的に自立してる感が良い。ビジネス上の仕方のない同行者って感じ。
かと思えば
そして、そのために、「両手」が、わたしたちをさし招いて、来いという合図をした時、妻はわたしを指さし、わたしは妻を指さし、妻はわたしに、まず先に、むりやりに行かせようとし、わたしは妻を押して先に行かせようとして、妻とわたしは、お互いに相手を敵に売ったのだった。 p.84
こういうシーンがあるから面白い。妻もわたしも生き生きとしてて良いね。
さて、白い木の内部に入る前に、わたしたちは、戸口の男に、七十ポンド十八シリング六ペニーで、「わたしたちの死を売り」渡し、同様に、一ヶ月三ポンド十シリングの金利で「わたしたちの恐怖を貸与」してしまっていたので、わたしたちはもう、死について心を煩わすこともなく、恐怖心を抱くこともなかったのだった。 p.85
おいおいおいおい・・・こういうことが些細なことのように流されていくのほんと最高。夢中で読んでたらスルーするぞ。
てか「わたし」の神様設定はどうなったんだ。神って死ぬの?
誠実な母、マジで誠実だった。こういう、過酷な旅の途中で唐突に現れるめちゃくちゃ良くしてくれる人物って「注文の多い料理店」にしろ「雪女」にしろ、実は主人公らを食おうとする悪者だと相場が決まっている(たしか岡崎京子『僕たちはなんだか全て忘れてしまうね』にもあったな)のだけれど、この作品にそんな"相場"なんてものは存在しない。
いやー木の中に入るときに死と恐怖を買い取られた時点で絶対よからぬ事を企む施設だと思ってたけどな〜
本作のいいのが、自分の期待を裏切ってくれる点というより、そもそも期待や相場を裏切るつもりもないところで物語が紡がれているのだろう、ということ。
その根拠はこれがアフリカ文学であるから、などというメタな情報による面もなくはないが、何よりこの奇想天外な物語をここまで読んできて、そういうレベルの話ではないことがよ〜く分かっているためだ。
それから、わたしたちは、借主から「恐怖」をとり戻し、最後の金利を払ってもらった。そのあと、わたしたちから「死」を買いとった男を見つけたので、「死」を返してくれと交渉したが、それはわたしたちから買いとったものだし、代金もちゃんと払ったのだから、返すわけにはいかないと断ってきた。そこでわたしたちは、「恐怖」だけをもって、「死」の方は、買主の方に任せておいたのだった。 p.93
そうだ、「恐怖」を貸してたんだ。すっかり忘れてた。「死」を売り払って死ななくなるの得しか無くない?
──「この「赤い町」の住民はすべて、昔は、人間だったのです。その頃はわたしたち人間の目はすべて、ヒザに付いていたし、また引力の関係で、空に向けてかがんだし、歩き方にしても、後ろ向きに歩いて、決して現在のように前向きには歩きませんでした。 p.96-97
大ほら吹きの面目躍如といった有様。
物語って、何よりもまず想像力の賜物だったな、ということを思い出させてくれる。
わたしはもちろん、彼らの言うことなどには耳を貸そうともせず、彼らをアミとワナから取り出して、火に入れようとしたのですが、彼らはなおも、自分たちを絶対に火の中に入れてはならないと、誇らしげに、くりかえして言うのでした。 p.98
川の赤い鳥と森林の赤い魚を火炙りしようとしている場面。「誇らしげに」ってのがなんかいい。彼らのプライドや価値観が伝わってくる。
妻はその時、こんな謎めいたことを言った。──「このことによって短い期間、一時的には女を失うことにはなりましょうが、男を恋人から引き離す期間は、もっと短いものになりましょう」妻は、預言者のように、比喩を使って話したので、わたしには、その言葉の真意は、つかめなかった。 p.101
いきなりどうした妻!?こっちも真意をつかめないよ。
実は、その女は、大きい方の「赤い木」の前にいた「赤い小さい方の木」でした。そして大きい方の「赤い木」は、「赤い町」と「赤い森林」の「赤い住民」の「赤い王様」であり、大きい方の「赤い木」の「赤い葉」は、「赤い森林」の中の「赤い町」の「赤い住民」たちだったのです。 p.109
は????(最高)
そして一旦その町の住民全部と森林の生物が一緒におどりだした時、まるまる二日間ぶっつづけにおどり、誰もおどりをやめさせることはできなかった。しかし「ドラム」はやがて、自分がこの世の者でないことをさとって、ドラムを打ちながら天国へ帰って行き、その日からは、二度とこの世に姿を見せなくなった。すると今度は、「ソング」が歌いながら、意外にも、大きな川に入って行き、それが、彼の姿のこの世での見納めということになってしまったのだった。そして最後に「ダンス」は、おどっているうちに山になり、その日以来プッツリと消息を断ってしまった。そこで墓から起き出してきた死者たちはみな、また墓へ戻り、その日から二度と起き上がることができなくなってしまい、のこりの生物たちもみな、森林などに戻って行き、その日以来、彼らは町へ出て、人間とか、その他の類と一緒におどることができなくなったのだった。 p.111
かなしい・・・。踊り始めるのも解散するのもスピード感がすごい。「意外にも」大きな川へ入って行き、ってどういうこと?山になったのなら消息は掴めているのでは?などという無粋なツッコミをしてはいけない。
そこでわたしは、彼に金を貸したものかどうか、妻に相談すると、妻は、この男は「すばらしくよく働く労務者ではあるが、将来きっとすばらしい泥棒にもなりましょう」と言った。もちろんわたしには、妻の言った言葉の真意はわからなかった。 p.113
おい!!!わかれよ!!!真意てかそのまんまじゃねえか!!!まさか前の「比喩を使って話す予言」が前フリだとは思わんかったぜ……
五分間ばかり、彼らはそのようにじっとわたしたちを見つめてから、その一人がわたしたちに、どこから来たのかと訊いたので、わたしは、わたしの町から来たと答えると、その町はどこにあるのかと訊くので、この町からずっとずっと遠く離れた彼方ですと言うと、彼は、その町の住民は生きているのか、死んでいるのかと訊きかえすので、その町には死んだ者は一人もいませんと答えた。 p.128-129
このまったく「文学的に洗練された文章」とはほど遠い冗長なやり取りよ。最高
「美文」を書くという三島由紀夫や堀江敏幸に見せてやりたいね
そしてわたしたちが、彼の合図に答えられないのをみて、彼は、わたしたちのところへきた瞬間から、わたしたちと一緒にその町で住むわけにはいかないことに気がつき、話をはじめる前に、わたしたちのために、小さな家を建ててくれた。 p.131
こういうとこやぞ!!!さらっとスピード建築すな!!!
やがて森林の奥深く入りこんだ時、彼は、彼と同類の生物に出会った。すると彼は足をとめ、二人で袋を今度はあちら今度はこちらという具合に、放り投げては、拾い上げ、しばらくの間そんなことを何回かくり返しているうちに、袋の投げ合いをやめ、彼は元通りに、黙々と歩き続け、夜が明けるまでには、例の道路からは三十マイルも奥に入っていた。 p.140
袋の投げあい全く意味分からなくて不気味ですき
そして、この九人の生物と一緒に農園で働いていたある日、その一人が、何を言っているのやらわたしにはわけのわからぬ彼らの言葉で、わたしをののしったので、それがはずみでけんかになり、わたしに殺意があるのを見てとった残りの連中が、次々にわたしに組みついてきた。わたしは、最初に立ち向ってきた生物をまず殺し、そのあと二番目に向ってきた生物もという具合に、次から次へと血祭りにあげ、いよいよ最後に、彼らのチャンピオン格の生物だけが残った。 p.143
いやお前のほうが強いんかい!!!謎の生物の描写あれだけ恐ろしかったのに……クソワロタ
やがて、彼の姿がほとんど見えなくなってしまったその瞬間、ふとわたしの心に、わたしと一緒に森林をさまよいながら、「死者の町」までわたしについてきてくれた貞節な妻、そしていかなる苦難にも、決してたじろがなかった勇気ある妻のことが浮かんできた。そして妻は、このようにわたしから決して離れなかったのだから、わたしだって、断じて「飢えた生物」が妻を連れ去るままに放っておいてはならないと、自分に言ってきかせた。 p.149-150
激アツ展開。どうした?普通の小説みたいじゃないか
さてこの「混血の町」には、土着民の法廷が一つあって、わたしはいつも出廷して、多くの裁判を傍聴していた。ところがある日、驚いたことに、友人に一ポンド貸したある男が法廷にもちこんだ裁判を裁くように、依頼をうけたのです。 p.151-152
いきなり法廷パート始まって草
というかいつも裁判を傍聴していた時点でツッコみたい。
そしてこの依頼されたエピソードのハチャメチャさがすごい。自分も「私の職業は、金を借りることだ。わたしは借金を頼りに生活しているのだ」と言い切りてぇ〜〜〜
寓話的になりそうなのにならない(それでいてちゃんと裁きがいのある)のがすごい
そんなわけで、「混血の町」の住民たちはみな、ひたすらわたしに戻ってきて、両案件の判決を下してくれることを切実に願っている次第ですので、もしも、この物語をお読みの方の中でどなたかこの二件とはいわず、一件でも結構ですから、可及的にしかるべき判決を下され、その内容をわたし宛にお送り頂ければ、これにまさる幸いはございません。 p.158
だからいきなりこっちに話しを向けられたらビビるって! この物語、どういう位置づけでこのひとは語ってるんだ?
マジか〜〜頼まれちゃったよ〜〜ゲラゲラ笑いながら両案件を聞いてたのに笑ってる場合じゃねえ
そこで彼らがわたしに何か手を出す前に、わたしは自分を、さっさと、平たい小石に姿を変えてしまい、自分で自分を投げながら、故郷への道を急いだ。 p.161
でた!!!僕の好みの自己撞着案件だ!!!
稲垣足穂『一千一秒物語』の「ポケットの中の月」
ある夕方 お月様がポケットの中へ自分を入れて歩いていた 坂道で靴のひもがとけた 結ぼうとしてうつ向くと ポケットからお月様がころがり出て 俄雨にぬれたアスファルトの上をころころころころとどこまでもころがって行った お月様は追っかけたが お月様は加速度でころんでゆくので お月様とお月様との間隔が次第に遠くなった おうしてお月様はズーと下方の青い靄の中へ自分を見失ってしまった
みたいなやつ。
最後までわけわからんまま駆け抜けたなーー。普通そこは主人公が「天の神」へと御供物を奉納しに行くとこでしょ。最後がぽっと出の奴隷・・・。未完のまま作者死んだ?ってくらい唐突な終わりだな。
読み終えた!!!最高!!!!!
「これぞ海外文学」って感じ。自分の身近な世界とは何もかもが違う世界の語り方に出会わせてくれる。
「先進国」かつ「未来」に生きる私の立場からこういうアフリカ文学のエキゾチシズムに触れて大絶賛するのは、それはそれでオリエンタリズムっぽくて自省はしなけれないけないけど。最高だった。
初心者向け海外文学リストにこれは絶対入れたい。短いし読みやすいうえにバカバカしくて面白い。
小学生でも十分に読めそうというか、むしろ子供こそ本作を純粋に楽しめるかもしれない。
こないだ読んだオネッティが「何が起こっているかではなく、いかに語るか」で魅せる小説だったのと対照的に、『やし酒飲み』はひたすらに「〜〜した。〜〜だった。〜〜でした」という出来事の羅列が息する間もなく続く。とにかくスピード感がすごい。ただし「いかに語るか」に魅力がないわけではなく、敬体と常体が混じった、やや冗長で「駄文」とさえ言ってしまえるかもしれない独特の文体が内容のわけわからなさにこれ以上なく適している。内容・文章ともに至高の文学作品だと思う。
小説というよりも童話に近い。ガルシア=マルケスの小説でさえ、このドタバタ感・スピード感には敵わないんじゃないか。
いちばん連想した他作品はアレナス『めくるめく世界』。世界観も倫理観も何もかも我々の常識とはかけ離れている奇想天外な冒険譚。
ただし、本作の前ではアレナスでさえもまだまだ前衛的な文学性を真面目に志向している「お利口さん」の文学だったんだなぁと思う。アレナスがお利口さんってマジかよ。
「死者」が「定年退職したひと」くらいの感覚で平然と登場してくるのは『ペドロ・パラモ』とかラテアメ文学でもありがち。
主人公(と妻)、旅の先々で死にそうな目にあっては命からがら逃げているけど、しれっと大虐殺もしている。
こういう世界観・文体をトレースして現代日本に舞台を移した小説を読んで/書いてみたいが、卑近な舞台だとこうはならないかなぁ。風刺性がどうしても無駄に生まれてしまいそう。
一時期Twitterでバズったなろう小説『すばらしきアッシュ』にも少し似ているかも。小説の文法作法を逸脱している感じが。
私は大真面目に『アッシュ』は"世界文学"だとみなしている。「緑色のドカーーーーーーーーーン!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」という冒頭は、『重力の虹』の「一筋の叫びが空を裂いて飛んでくる」にもまったくひけをとらない。
上でオリエンタリズムと言ったような、拙い文章を「安全圏」から逆に面白がって持ち上げて持て囃すような姿勢を幾らかも含んでいないか、と問われたら、否と断言することはできない。
ただ、わたしの今の文学観・好みでいえば、こうしたエネルギーのある独特の文体の小説は諸手を上げて評価したい。
「わざと拙くてぶっ飛んだ小説を書く」ことは非常に難しく、その達成には文学的価値があると思う。
訳者あとがき、勉強になる。多和田葉子の解説、まぁまぁ良い。(いかにも多和田葉子が好きそうな小説ではある)
大学生のときにラテンアメリカ文学に出会って好んで読んできたけど、アフリカ文学もめちゃくちゃ好みな可能性が高いと、本書を読んで思った。ようするに自分は、自分から「遠い」作品をもとめて海外文学を読んでいるので、こうしたエキゾチックな香り全開のものが好きなんだろう。
これまでに読んだアフリカ文学・・・今パッと思い浮かぶのは南アフリカ出身のクッツェー『恥辱』だけど、これは普通にお行儀のいい正統派ヨーロッパ文学という感じで駄目だった。アチェベ『崩れゆく絆』とか読んでみたい。『やし酒飲み』のだいぶあとにチュツオーラが書いた『薬草まじない』も気になる。
あと、アフリカ人初のノーベル文学賞受賞者の劇作家ウォーレ・ショインカも読んでみたい。