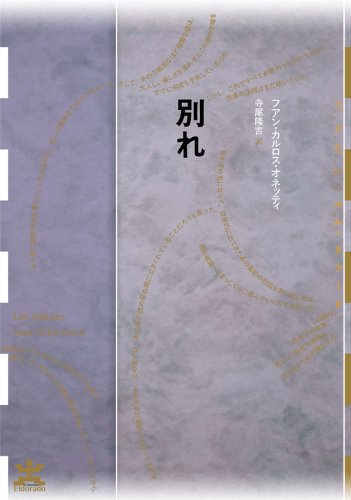前記事に引き続き、『別れ』に収録されたもう1つの短編「失われた花嫁」(1968)を読んだ。
「この恐ろしい地獄」で、そのレトリカルで難解な文章に驚き感動したが、この短編では文章の凄さというより「語り」が凄いと言ったほうが適切である。
この単行本の帯の背には「鮮やかに織りなされる語りの妙技」と書かれているが、まさにこのフレーズの通りに"妙技"としか言いようがないほど凝った語りによって本作は編まれている。
本作は、1人で結婚の幻に浸り続ける狂った花嫁の哀しく美しい姿──を、見守り続ける「私たち」サンタ・マリアの住民の物語である。多分。
例によって今回も物語の正確な筋や細部を一読ではほとんど掴めなかったが、おそらく何度読んだとしても掴みきれないようにわざと曖昧かつ錯綜させて書いている。
本作に感じたいちばんの魅力は、上記の通り、失われた花嫁の行動描写が幻想的で美しいところだ。しかも、それを「私たち」住民が見たり見なかったりするという、観察者と対象の距離感や隔絶が、その美しさ・哀しさをより引き立たせる仕組みになっている。
本作の真の主人公は花嫁でなく「私たち」であり、そして秋のサンタ・マリアという町そのものである。オネッティが創作し、彼の多くの小説の舞台となる町が変わりゆく様への郷愁が、花嫁の人生と共鳴してうまく描かれていた。
以下、付箋を貼ったところ
私が患ったあのサンタ・マリアの秋、何の共鳴も、何の事件もないまま、三月十五日という日がごく普通に、女性がハンドバックに入れて持ち歩くティッシュペーパーのように柔らかく、紙、それもただの紙ではなく、尻の間をそっと滑る絹紙のように優しく始まった。 p.123
どんな比喩だよ
モンチャよ、この物語もすでに誰かの手によって書かれていたというし、たいしたことではないが、アメリカ人の手で解放されて分離した南部だか、ブラジルのどこかの町だか、ヴィクトリア時代伝来のイギリス伯爵領だかでは、このすべてはすでに別のモンチャによって体験済みなのだという。 p.124
言葉は事実を凌ぐ、お前にはもうその意味がわかるだろうか。 p.125
これはオネッティの小説そのものの説明っぽい。作中の「事実」とでも呼ぶべきものが読んでも判然とせず、事実を「言葉」そのものが上回っている。だから、何が起こっているかを気にすることなく、ただその言葉の連なりに身を任せるのがこの作家の小説に合った読み方なのではないかと思う。
私はただ黙って、女であるお前、両脚の間に真のお前を避けがたく包み隠したお前に当然支払われるべき敬意を、周囲にまで押しつけていた。 p.126
策略、手立て、謙虚さ、真実への愛、明確さの追求、秩序立った語り、そうした必要性から、ここで「私」は姿を消すことにして、以後「私たち」で話すことにしよう。誰もがそうしてきたのだから。 p.127
すごいポストモダンっぽい。これ以降「私たち」が主語になるかと思いきや、普通に「私は」のままなのウケた。しばらく経ってからちゃんと「私たち」に変わる。
誰もが旅に出るわけではなくとも、誰もがこの町へ戻ってくる。ディアス・グレイも、一度もこの町を去ることなく戻ってきた。 p.129
「一度もこの町を去ることなく戻ってきた」って表現いい。使いたい
四頭馬車から、オレンジの花の匂いから、ロシア製の革座席から降りてくる女。私たちの頭のなかで巨大化し、物珍しい草木が伸びたあの庭で、容赦ない落ち着きを漂わせながら、シャクナゲとゴムの木の間で方向転換することもなければ、ありもしない香りを打ち消すこともなく、代父の腕にまったく重みのない体を寄せかけたまま進んでいく女。唇も舌も歯もない代父が、心のこもっていない型通りの古めかしい言葉を耳元で囁き、男として当然の上品な恨み節以外には何ら力を込めることもなく、彼女を花嫁に捧げ、月と衣装に白く輝くあの手入れの悪い庭で、彼女を結婚へと押し出す……
そして、明るい月夜ごと、再び軽く震え出した幼い手を伸ばし、指輪を待つ儀式を繰り返す。この凍てつくような寂しい公園で、亡霊の前に跪いた彼女は、空から滑り落ちてくるようなラテン語のいつも変わらぬ響きに耳を傾ける。喜びのときも悲しみのときも、健やかなるときも病めるときも、死が二人を分かつまで、愛を誓い、助け合うこと。
不遜なほど高い塀に四方を閉ざされたまま、私たちの平和な日常とは何の関係もなく、冷酷な白い月夜ごと、疲れも希望も知らず、この世のものとも思えぬこのあまりに美しい儀式は繰り返された。 p.131
ここが本作の白眉(のひとつ)。長く引用してしまった。幽霊譚とかゴシック小説みたいな雰囲気もある。
だから私たち、私たちの誰もが、予感も良心の呵責もなしに、短い第一部へ、何も知らぬ者たちのために書かれたプロローグへと彼女を導いていったのだ。 p.137
バルテー薬局の助手だか、愛人だかとなっていた屍集めのフンタはすっかり成長して、体も強く、大きくなっており、かつての内気な姿を彷彿とさせるものといえば、一瞬の白みを帯びた微笑みだけだった。 p.140
『屍集めのフンタ』(1964)ってオネッティの代表長編のひとつだよな。〈サンタ・マリア〉サーガとして繋がっているということかな。というか、薬局のバルテーもいきなり出てきて人物像が掴めなかったが、この長編を読めばわかるのだろうか。書いたのは『フンタ』のほうが先だから辻褄は合っている。
将来サンタ・マリアの生活と情熱についてあれこれ思索を巡らせる者もいるだろうから、彼らを喜ばせ、当惑させるために付け加えておくが、この時点ですでに二人の男は小説から、その揺るがぬ真実から外れていた。 p.143
理解できない人もいるかもしれないが、他のすべて、つまり、私たちサンタ・マリアの住民が相変わらず現実と呼ぶものは、モンチャにとって、健康であれば自動的に更新されていく生理的活動と同じく、まったく単純なものにすぎなかった。 p.150
大事なのは、みんなで協力して彼女の姿を再現したことだ。 p.151
いずれにせよ、ほとんど何も起こってはいなかったのだ。何を見ても、何もわかることなどなかった。ただ見ているだけだったのだ。 p.152
これも本作を読む読者自身への注釈として機能できる一節。しかしこうした読みは陳腐だし何も読んでいないのと変わらないようにも思えるので控えたい。
→続き:表題作を読んだ