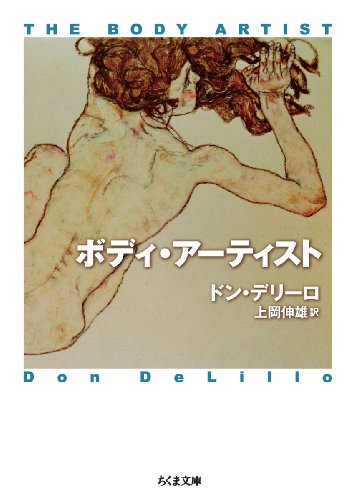上岡伸雄 訳(ちくま文庫 )で読んだ。
初デリーロはこれと決めて昨年の11月に読み始めたが序盤で放置しており、ちょうど本作でオンライン読書会が開かれるということで数時間前に読み終えた。
付箋を貼った文を引用しながら読んでいる最中に思ったメモを記す。
第1章
こういうとき、あなたはより確かに自分が何者であるかを知る──嵐が過ぎ去った後の陽射しの強い日、ほんの小さな落ち葉でさえも自意識に刺し貫かれているような日に。 p.10
「ほんの小さな落ち葉でさえも自意識に貫かれているような日」って表現すごいな、と読み始めて思った。
静謐な文体。夫婦間のややズレた異様な会話。日常的な動作を執拗に描写する。
10ページ以上の前の発言に返答する(その間は別の些細な話題に逸れていたり、些細な動作の描写が挟まったりしていた)
鳥たちは餌台から羽の音を立てて飛び立った。羽の音はみなbの音とrの音だった。bの文字の次にビブラートのrがいくつも続く。しかし、実際はまったく違っていた。それでは羽の音を表したことにならないのだ。 p.26
ポストモダン文学らしい人を喰ったような描写の訂正。しかし全体的に文が静かというかスローなのであまりおふざけ感がなく少しこわい。
あなたは新聞の日曜版を他の部分から分ける。 p.30
あなた?二人称?「彼女」(妻)のこと?夫婦とは別の人物を指す?
→その後もちょくちょく二人称があるが、どうやら妻を指すっぽい。そもそも冒頭(p.10)が二人称
p.41
突然第1章が終わった。終わりそうなところで終わらず、終わらなそうなところで終わった。
自死したという映画監督のレイ・ローレンツは第1章の男性(夫)だと思うが、女性(妻)はレイの3番目の妻でボディ・アーティストのローレン・ハートケ?
「最後の朝のことだった」p.10 とあるように、第1章はおそらくレイの自死の日の朝のこと。彼は午前中にマンハッタンのアパートで発見されている。しかもアパートの居住者はレイの最初の妻でファッション・コンサルタントのイザベル・コーラス
第1章の家はマンハッタンぽくない。自然に囲まれてる感じ。というか2階とか言ってたからアパートではない。
レイは1章のあとマンハッタンに移動して自死した?……とするとあの女性はローレンである可能性が高い。
第2章
やはり章の冒頭だけ二人称
すべてが緩慢で、靄がかかり、空っぽで、そしてそれはすべて「……のように思われる」という単語との関わりで起きている。 p.48
ここもメタというか語りの言語を再帰的に語る。
「胸に重い痛みを感じながら」p.49 や「最初の頃、彼女は車から降りると崩れ落ちそうになった」p.52 など、ローレンが夫を失った悲しみや喪失感や虚脱感が意外と率直に語られている。
p.59
新聞、ラジオの天気予報やニュース、そしてコンピュータでのフィンランドの道路のライブ配信……メディアによって空間的に離れた世界と繋がり、今この場の自己の身体性に影響が及ぶというのは『ホワイト・ノイズ』など他のデリーロ作品にも共通する要素か。
彼女はその翌日、小さな寝室で彼を見つけた。 p.64
これ最初、夫が生き返ったか幽霊になって現れたと思ってビビった。どうやら別人らしい。
しかも少年かと思ったら彼女より年上
3ヶ月位前から彼のたてる物音が聞こえていたようだけど、どうやって来たのか。非リアリズムではないよね。
第3章
彼女は彼が横向きに家の中に入って行くのを見た。少し足を引きずるように歩きている。おそらく浮遊するのを恐れているのだろう。 p.71
最後の1文好き。
素朴に、もし自分がローレンだったら1人で住む家に前から見知らぬ成人男性が住み着いていたらめちゃくちゃ恐ろしいんだが。女性と男性という意味でも。ホラーもあるし、性加害や犯罪的な意味でも怖い。しかしローレンはそうした反応はまったく見せない。それは夫を亡くした虚脱状態だからなのかもしれないが、現実的に考えたらそういう弱っている時に遭遇するのは余計にたちが悪いし恐ろしい。
ローレンは彼を最初から自分に危害を加える存在ではないと感じていたことになる。
その声の端には何かがあった。収入のレベルとか、動詞の時制とか、両親がテレビで何を見ているかとは関係のないものが。 p.80
この並びに動詞の時制を入れるところが示唆的。1ページ前でまさに過去形から現在形への転換について書いているのでそのことだろう。
タトル先生とレンツとローレンが互いに同一化して入れ替わる。p.81の最後らへんどうなってるんだ。
第4章
こうした言葉はすべて間違っている、と彼女は思った。 p.86
典型的ポストモダン
僕が思うに、きみはきみひとりの小さな全体主義社会を築こうとしているんだよ、そうレイはかつて言った。もちろん、きみはその社会の独裁者なんだけど、同時に抑圧された民でもある。 p.93
この言い回しどっかで聞き覚えがある。→と思ったら、以前相互フォローだった人のプロフ欄で引用されてた。
これはエロチックであると同時にエロチックさのパロディでもあった。 p.94
レイの最初の妻イザベルからの電話。めちゃくちゃマウントとってくるなこの人。
私たちは二人でひとつの人生を生きていたけど、それは彼の人生だったの。 p.96
ここだけ切り取るとフェミニズムっぽい。
彼女は考えた。おそらく、彼は物語性を持たない時間の流れの中で生きているのだろう。 p.106
示唆的……というより露骨。説明的過ぎ。
タトル先生の支離滅裂な感じ、オースター『ガラスの街』の序盤に出てくる依頼人?にちょっと似てる。
夫の影をタトル先生に見ることは、精神的な不倫とトラウマからのリハビリを同時にやっているようにも思える。
第5章
彼女はこれを何と呼んだらよいのかわからなかった。歌を歌っているのだ、と考えてみた。 p.122
日常言語(リアル)として意味不明でも、歌や詠唱(フィクション)としてなら受容できる。
タトル先生の思考・発言が地の文のレベルまで浸透していたらアイラやアレナスやコルタサル(悪魔の涎)のような「ヤバい」センサーに引っかかったかもしれないが、あくまで彼のカッコ「」の中にその異様さが閉じ込められており、それを異様だと感じるローレンに語りの水準があるので、それほど刺さらない。むしろ、彼女が彼をどう受け止めてどう接していくか、彼にどう影響されるのかがポイントだと思う。
p.126
時間の連続性を認識できない人を描くのはいいんだけど、それを客観的に説明的に描写するのが好みでない。そんなの大したことなくね?と思ってしまう。語り自体に彼の主観を憑依させてくれれば面白かったんだけどなぁ。
大柄な男が突然、彼女の頭上に現れる。それは外界からの衝撃、打撃、侵害されたという驚き。その瞬間の表象のされ方は、見る側を心底震え上がらせる──ずっと隠遁生活を送ってきた二人の人間、自己に没入できる環境で暮らす人間たちにとっての脅威。 p.129
突然映画的な描写が始まってびっくりしたが、よくよく読むとそんなに変なことは言っておらず、ローレン視点ですべて理解できる。単に比喩として映画やらショットやらを使っていただけだった。
彼女は犬の比喩を使わないようにする──彼女の想像上の話だが。この家主と同様、迷子になった飼い犬が家に戻ってくるといった比喩をタトル先生に当てはめたりはしない──良心の呵責からであれ何であれ。 p.131
これ何でだろう。やっぱりローレンのタトル先生に対する認識や思いの部分がいちばん興味深い。
彼の名を呼ぶのはいつでもひとりきりで、テープレコーダーに向かって話すときだけだった。なぜなら、もちろん──そうなのだ──その名前がかわいくて、相手を見下しているからだ。 p.134
そして彼女は、自分がこの場面を心の中で人に解説していることに気づいた──その人とはマリエラかもしれない、そうではないかもしれない──まるで彼が発見された芸術作品で、彼の有用性という問題に関して二人きりで話し合う必要があるかのように。 p.134
ローレンがタトル先生をいかに認識し、いかに描写するかがポイント。
カオティックなリアルと対峙した人間(フィクション)はどうするのか。
バカね、面白いことなんてたくさんあるわ、でも真実には全然近くないのよ。 p.136
いかにもラインマーカーを引きやすそうな文
5章終わり
うーん説明的すぎ!
皮膚を削ってその片に想いを馳せるとか、〈身体性〉というタームで批評しやすそうなところとか、いかにも文学的で苦手
静かに、日常の細部に潜む輝きと深淵、記憶と生──みたいな雰囲気は朝吹真理子『きことわ』っぽくもある。
それから、記憶と記録の再現といえばカサーレス『モレルの発明』も思い出す。
第6章
章の始めは例によって二人称。「クリップを落とす」たったこれだけのことでこんな文章を作文できるのは流石にすごいというか面白い。物量でゴリ押された。
「どういうわけか」。言語の中でも最も弱い言葉。それから「多かれ少なかれ」。それから「多分」。彼女はいつでも「多分」と言っている。 p.153
「どういうわけか」とか地の文でも結構使っているイメージがある。曖昧にしたり言ったことを否定したりと、主観性を持たせている印象。
原語が気になる。somehow, somewhat, probably? いやmore or lessか。
彼はこの状況に気づいていなかったのだ。彼女はそう確信した。でなければ、このことが自分の人生の条件にあまりにもぴったりであると考えており、これに気づくことも気づかないでいることも彼にとってはまったく同じだったのだ。意識の中でほんの小さな地位しか占めなかったのだろう、夏の日に小さな咳をする程度にしか。 p.156
最後がすき。「ほんの小さな地位」の比喩として「夏の日の小さな咳」を持ってくるの格好良い。
「ボディ・アートの極限」
旧友マリエラによるローレンのボディ・アートに関する記事。
ボディ・アートの内容はこれまで書かれてきた彼女の行動(車道のライブ配信、タトル先生との交流)がほぼそのまま反映されていた。
ローレンとタトル先生の会話がテープレコーダーで録音されていたように、この記事を書くインタビューの席にもボイスレコーダーが置かれていたのは象徴的だ。
身体と声についてはやや気になる。ここまでボディ(身体)が強調された作品でありながら、その内実はタトル先生がレイやローレンの声真似をするという〈声〉性にかなり頼っている。声も体の一部、あるいは体のどの部位よりも身体性を発露するツールである、みたいな捉え方なら丸く収まりはする。
ボディ・アート最中は身体は変わりまくるのにあくまで録音した音声に合わせて口パクで、インタビュー時にはじめて声の憑依を披露してマリエラを驚かせる。声が変わるより身体が変わるほうが非現実的でショッキングだと思うのだけど、そこらへんの転倒が果たして転倒のつもりでやっているのかよく分からない。
それは我々が何者なのかに関わるのだ。自分たちが何者かを練習していないときに我々が何者なのか。 p.179
第7章
彼女はノズルを持ち、噴出口を頭に向けて、プラスチックの引き金を指で引いた。刺激を強めるために舌を突き出して。
これが人々のすることなのだ、と彼女は考えた。 人々がたったひとりで生きているときにすること。 pp.187-188
浴室の掃除中にふと消毒スプレーを自分の頭にかける。ここはひりつくような哀しさがあって良い。
素晴らしいアイデアではないか、手がないなんて。これは日本人女性に関して知るべきことすべてを表わしているし、パフォーマンスにはうってつけであったろう。 pp.189-190
思い切りのいいわけわからん偏見が炸裂しててすき。
このようなことを現実に目にしても、なお想像できないのか? p.201
想像が現実を上回るのではなく、現実が想像を越えていく。現実が想像の余地を塗り替えていく。
最後らへんはタトル先生が再び帰ってきたのかどうか判然とせず、彼女の記憶と動作の自制が錯綜し、わりと前衛的な文でクライマックス感を煽る。しかし1章と同様に、終わりそうなところで終わらず、わかり易く落ち着いたところで終わる。
うーむ、微妙
読み終えた。
訳者あとがきによれば「この小説の醍醐味は、言語の崩れ、時間認識の崩れが、言語によって再現されていることだろう。」ということだが、それが全然面白いと思えなかった。想像を超えず、「まぁこういう小説もあるわな」という感じ。難解ではなくむしろありきたり過ぎる。
川上弘美による短い解説(というか短評)も無難でつまらない。
うーん……デリーロ合わないかも……
基本的に地味だと噂のデリーロ作品のなかでもまだ自分が興味を持てそうな部類として『ボディ・アーティスト』を選んだのだが、これでもダメとは……。なんとなくダンスに近いのかなと思って読んだけど、ボディ・アート思ってたのと全然違った。
『ポイント・オメガ』とか更に合わない可能性あるな。逆に『ホワイト・ノイズ』『アンダーワールド』のような大長編のほうが好きかもしれない。読み通せる気まったくしないけど。(ホワイト・ノイズ新訳&リブラ復刊まだ?)
ピンチョンやギャディスを初めて読んだときのような「な、なんじゃこりゃ〜〜〜〜」という驚き、自分の小説観を覆してくるヤバさがまったく感じられなかった。上で多数引用したように、部分部分では「おっ」となる文もそこそこあったが、全体としては「読んで良かった〜〜!!!」とは思えない。(まぁようやくデリーロ1冊読めたという実績解除の嬉しさは大きいが)なんかな〜こういうのだったら国内文学でも普通にありそうな気がするんだよな〜古井由吉とか?(読んだことないけど)
こういうテーマや文体が好きで大絶賛するひとがいるのはわかるが、自分の好みではなかった。